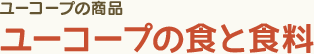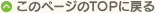- トップページ
- ユーコープの商品
- ユーコープの食と食料
- 産地からのたより:活〆銀鮭の産地から
産地からのたより
2016年5月にグリーン・プログラム商品としてデビューした宮城県産活〆銀鮭。 女川町と石巻市雄勝町(おがつちょう)の6軒の生産者が切磋琢磨しながら養殖に取り組んでいます。 このグループで一番若いタクちゃん(本名:千葉拓実さん)が、毎日の仕事のことや身の回りの出来事などを、写真とともに幅広く知らせてくれます。
- ユーコープの商品トップ
ユーコープセレクション
- 野菜・果物
- 精肉・加工肉
- 海産物
- 牛乳・乳製品・鶏卵
- デイリー食品
- 調味料
- 常温加工品・米
- 菓子・飲料・酒
- レシピClip
- ユーコープの考える「食の安全・安心」
- ユーコープの品質保証の取り組み
- 商品検査センター
- 放射性物質に対する考え方
- ユーコープの約束
- 商品Q&A
- 商品情報検索
- みんなの声で、コープの商品をチェック!

- 産直データブック